入院費用の支払はいつまで? 病院のお金が足りない時の対処方法も解説

入院により高額な費用が発生した場合、「病院への支払を後日にしてもらいたいが、いつまで猶予があるのか」「期限内に支払えなかったらどうなるのか」と不安に思う方も多いでしょう。
この記事では、一般的な支払期限や入院費用の平均額、支払が難しい場合の対処方法や公的制度を解説します。あわせて、緊急で現金が必要な時に役立つ方法も紹介します。
目次
入院費用の支払はいつまで?

支払のタイミングや期限は病院によって異なるため、事前に把握しておくことが大切です。ここでは、一般的な支払期限や、期限を過ぎた場合に起こり得ることを解説します。
一般的な支払期限
外来受診による支払は受診当日が原則となりますが、入院による費用の支払は退院時もしくは入院中が基本です。請求書に支払期日が記載されている場合は、その期日までに支払いましょう。なお、請求書が発行されてから30日以内が支払期日といわれていますが、病院によって期限が異なるため、必ず請求書の期日をチェックしてください。
また、病院の受付や相談窓口に相談すれば、分割払いや後払いに応じてもらえるケースもあります。急な入院で費用の用意が難しい場合は、早めに相談することが大切です。
期限内に支払えないとどうなる?
期限までに支払ができなかった場合は、まず病院から電話や督促状などで連絡が入ります。連絡が取れない、催促に応じない場合は、入院時の書類に記載した保証人へ連絡が及ぶこともあります。
さらに、長期にわたり未払が続くと以下のリスクがあることを知っておきましょう。
- ・病院からの督促がある
- ・身元保証人へ請求書が届く
- ・弁護士から連絡が来て、最悪の場合法的措置が取られる
このような状況に陥らないよう、支払が難しいと感じた時点で病院や関係機関に相談しておくことが重要です。
医療費の種類と平均金額
医療費の内訳や負担額はさまざまです。診察料や検査料に加え、入院時の食事代や場合によっては差額ベッド代も必要になります。ここでは、自己負担の仕組や平均的な医療費の目安を紹介します。
医療費の自己負担
日本では公的医療保険制度により、年齢や所得に応じて自己負担割合が決められています。
- ・70歳未満:所得に関わらず2〜3割負担
- ・70歳以上75歳未満:一般・低所得者は1〜2割、現役並み所得者は3割
- ・75歳以上(後期高齢者医療制度):原則1割負担、一定以上の所得者は2割
この自己負担割合に基づいて、医療費が計算されます。
初診料や診療時の費用
医療費は、診療や検査などの医療行為ごとに「点数」が定められており、その合計点数に10円をかけることで費用が算出されます。算出後の金額から、個々の自己負担割合に応じた金額を医療機関に支払う仕組です。
初めて受診する場合には「初診料」、同じ医療機関で再び診察を受ける場合には「再診料」がかかります。その他にも、時間外や休日の受診では「時間外加算」「休日加算」、乳幼児の診察では「乳幼児加算」が加わる場合があります。
入院時の費用
病気やケガで入院すると、診療や検査にかかる費用以外に、公的医療保険の対象外となる食事代や差額ベッド代などの費用が発生します。入院が長期化するほど、医療費負担は大きくなっていきます。
生命保険文化センターが実施した「生活保障に関する調査(令和4年度)」によると、入院1日あたりの自己負担額は平均20,700円、入院日数の平均は17.7日です(食事代や差額ベッド代などを含む)。
最も多かった入院期間は「5~7日間」で、全体の27.5%を占めています。例えば、5日間入院した場合、平均で103,500円の自己負担が必要となります。
病院に支払うお金が足りない場合の対処方法
入院や治療にかかる費用は高額になることも多く、支払期限までに用意できないケースも少なくありません。いざという時に慌てないよう、対処方法を事前に知っておくことが大切です。ここでは、代表的な方法を紹介します。
家族や知人に支払の相談をする
まず検討できるのは、家族や親しい知人に相談することです。一時的な援助を受けることで金融機関からの借入を避けることができ、返済条件も柔軟に決められる可能性があります。
ただし、親しい間柄であっても返済計画を曖昧にするとトラブルにつながりかねません。金額や返済時期は明確にし、借用書を交わしておくと安心です。身近な人からの借入は、他の方法が難しい時の最終手段として考えておくといいでしょう。
医療ローンを活用する
医療ローンは、治療や入院など医療費の支払を目的にしたローンで、銀行や信販会社などが取扱っています。審査に通過すれば分割払いが可能になり、経済的な負担を軽減できます。
医療ローンについてはこちらの記事もご覧ください。 医療ローンとは?基礎知識から対象となる治療やメリット・注意点を解説
クレジットカードで支払をする
クレジットカードによる支払が可能な病院が徐々に増えてきています。急な出費や高額な費用が発生した際には、リボルビング払いを活用することで月々の返済負担を軽減しながら医療費を支払えます。
ただし、クレジットカードの利用は支払を先延ばしにしているに過ぎないことを認識しておかなければいけません。引落日に口座残高が不足していると引落ができず、延滞などのトラブルが発生する可能性があるため、十分な注意が必要です。
クレジットカードのリボルビング払いについては、こちらの記事もご覧ください。 クレジットカードのリボ払いとは?仕組やメリット・デメリット、支払方法について
医療保険を活用する
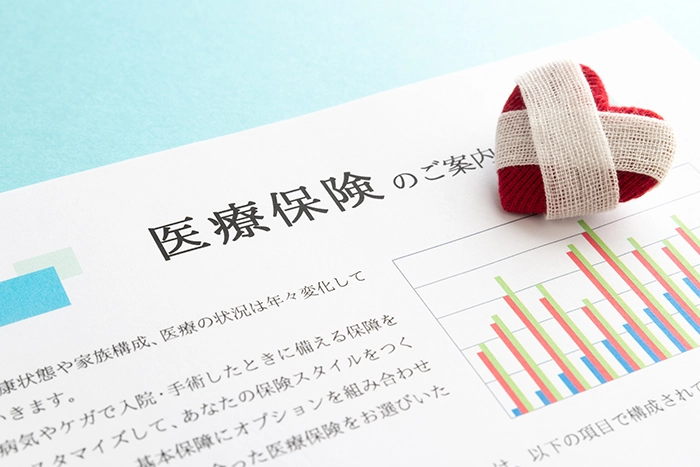
民間の医療保険に加入している場合は、給付金を申請することで最終的な自己負担を軽減できます。まずは保険契約の内容を確認し、今回の医療費が給付対象に該当するかを調べておきましょう。
給付金の申請を行う際は、診断書や領収書などの必要書類を揃える必要があります。申請方法や必要書類については保険会社の専用サイトや窓口で確認し、早めに書類を準備して申請手続を進めることが重要です。
クレジットカードのキャッシング枠を利用する
クレジットカードにキャッシング枠があれば、ATMやインターネットを通じて現金を借りられます。ただし、キャッシングは医療ローンやカードローンに比べて金利が高く、利用限度額も低めに設定されています。
よって、クレジットカードで支払ができず、現金のみの支払が必要な場合で、すでにキャッシング枠が設定されている、という3つの条件が揃っている時に限って検討する方法といえるでしょう。金利負担が大きくなる可能性があるため、できる限り他の方法を優先的に検討することをおすすめします。
カードローンを活用する
他の方法でお金を用意できない場合は、カードローンの利用も1つの手段です。審査を通過すれば利用限度額内で繰り返し借入・返済ができ、急な入院費の支払にも対応できます。
ただし、こちらも医療ローンなどと比べて金利は低くはないため、利用する時は返済計画を立て、借りすぎに注意することが大切です。
医療費の支払ができない場合の支援制度
病院に支払う費用がどうしても用意できない場合、国や自治体が用意している制度を利用すれば、負担を軽減できる可能性があります。ここでは、代表的な支援制度を紹介します。
負担を軽減する制度
医療費の支払が難しい時は、公的な制度を利用することで負担を抑えられる可能性があります。ただし、いずれも対象条件や申請方法が異なるため、必ず自治体や加入している医療保険の窓口にご確認ください。
無料低額診療制度
無料低額診療制度は、生活に困窮して医療費の支払が難しい世帯を対象に、一部の医療機関が無料または低額で医療サービスを提供する仕組です。住民税非課税世帯や生活保護受給者、失業などで収入が減少した人も対象となります。
利用するには、対象医療機関に直接申込み、本人確認書類や収入証明書類を提出する必要があります。対象医療機関は限られているため、事前に確認しておくことが大切です。
一部負担金減免制度
災害や失業などで生活が困窮している場合に、医療費の自己負担分を猶予・減額・免除できる制度です。対象となる事由には、世帯主の死亡・障害、住宅の損壊、事業の休廃止、失業、農作物の不作などがあります。申請は市町村の福祉事務所や医療保険組合で行い、被災証明書や収入証明書類が必要です。
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、通院による精神医療が必要な人を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。統合失調症やうつ病、不安障害、認知症、てんかんなど幅広い疾患が対象となります。利用が認められると自己負担割合が1割に軽減され、さらに月ごとの負担上限も設定されます。ただし、利用できるのは指定医療機関に限られるため注意が必要です。
高額療養費制度

1か月間にかかった医療費が一定額を超えた場合、超過分を払戻してもらえる制度です。上限額は年齢や所得に応じて異なり、70歳以上や低所得者には特例もあります。
事前に「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での支払を抑えられるため、入院や高額治療を控えている場合は早めに手続しておくと安心です。
高額医療費貸付制度
高額療養費制度は払戻しまで数か月かかる場合があります。その間に病院への支払が困難な時は、高額医療費貸付制度を利用することで、一時的に無利子で資金を借りることができます。一般的には払戻し見込額の8割程度を借りられますが、健康保険組合や自治体によって異なるため、事前の確認が必要です。
傷病手当金
会社員や公務員などの公的医療保険の被保険者が利用できる制度です。業務外の病気やケガで働けない場合で、休業が4日以上続き給与が支払われない時に受け取ることが可能です。最長1年6か月間、休業前の給与の3分の2相当額が支給されます。
なお、業務上で起こった病気やケガの場合は労災保険の休業補償給付の対象となり、傷病手当金と保障内容が異なるため、注意しなければいけません。
保険料支払が困難な時に利用できる制度
医療費だけでなく、健康保険料そのものの支払が難しい状況に利用できる制度が用意されています。
生活保護
最低限の生活が維持できない場合、生活保護を申請することも可能です。居住地の福祉事務所で申請し、収入や資産、就労状況の調査を受けたうえで支給が決定されます。ただし、生活保護受給中は車などの資産を持てないといった制約があるため、申請前に制度の内容をよく理解しておくことが重要です。
緊急で支払が必要な場合はプロミスのカードローンもおすすめ
ここまで、病院の支払期日や、お金が足りない時の対処方法、条件に応じて利用可能な各種支援制度について解説してきました。医療費の支払にはさまざまな選択肢が用意されていますが、すぐに現金が必要な緊急時や、お金の心配で治療を先延ばしにしている場合には、制度利用の手続や入金を待つ余裕がないこともあるでしょう。
そのような緊急時には、カードローンの利用を検討することもおすすめです。プロミスのカードローンでは、最短即日でのお借入も可能となっているため、緊急時にも迅速に対応することができます。 プロミスのカードローンをご検討中の方はこちら

